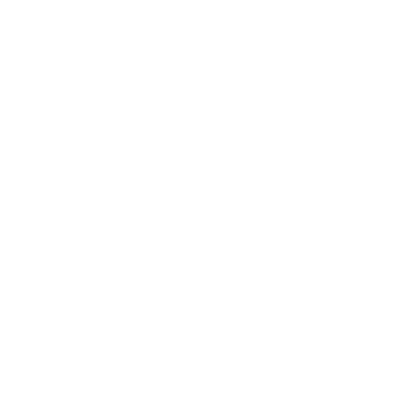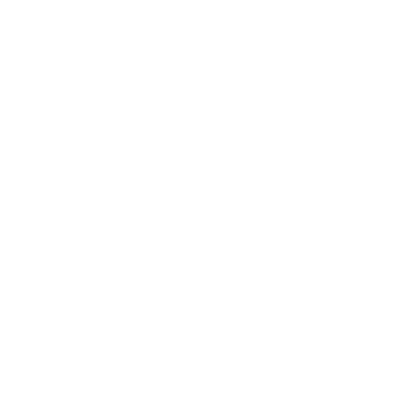私三代目藤蔭静樹は、藤蔭流を昭和6年に創立した初代の孫にあたります。
明治期、文学演劇等の日本文化の改良に取り組んだ坪内逍遥が舞台改革の最一段として、明治三十七年に「新楽劇論」を発表しました。
「日本舞踊」という語はその中で生まれた造語で、それまでは歌舞伎舞踊と言われていました。逍遥の舞踊改革の想いは、大正十一年まで続けられ、新舞踊運動に多大の影響を与えました。その新舞踊運動のはじまりは、大正六年初代藤蔭静樹の舞台公演といわれております。よって初代は日本舞踊家第一号と言われています。
宮城道雄曲の「落葉の踊り」「秋の調」などの歌詞のない器楽曲の振付、洋楽伴奏の踊り、群舞作品などを次々に発表しました。いずれもヨーロッパ近代の影響でした。
その先駆者として昭和三十五年に紫綬褒賞受賞。昭和三十九年に文化功労者として顕彰され、四十一年には勲四等瑞宝賞を受賞しております。
また日本舞踊の普及、若い世代への伝承に力を注ぎ、立命館宇治中学校の日本舞踊の授業にも講師として取り組んでおります。平成二十九年には文化長官表彰を受賞いたしました。
藤蔭流の舞踊は先師静樹が情熱を傾けた想像の世界であります。私も新作に取り組み、ジャズピアノ山下洋輔氏とのコラボ「ジャズ道成寺」など数々発表しております。また古典をも大切に藤蔭流の伝統舞踊常磐津「大工」や初代が大正十九年に発表しました長唄「思凡」を再演いたしております。
「型を重んじ型にとらわれず、心を潜めて心を踊る。」
先師の言葉を伝承してまいる所存でございます。