宗家藤蔭流
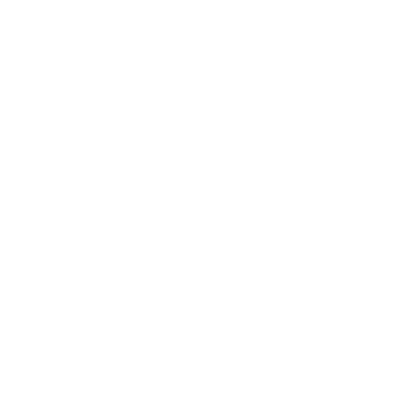
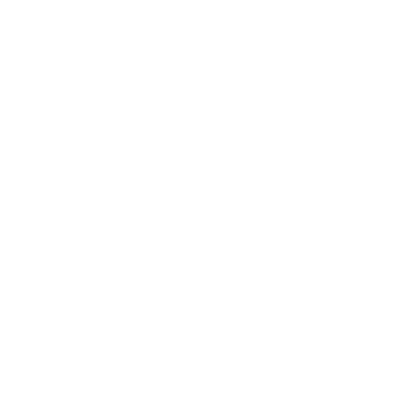

1903 藤間勘右衛門に入門
1909 藤蔭静枝の名を許される
1910 永井荷風との交流が始まる
1914 永井荷風と結婚
1915 離婚
1917 「藤蔭会」舞台公演開始
1929 パリ公演
1931 藤蔭流創流
1957 二代目に静枝を譲り、藤蔭静樹となる
1960 紫綬褒賞を受賞する
1964 文化功労者に選出される
1966 没
初代静枝を語る際に避けては通れないものが、永井荷風との縁です。
新橋で芸妓八重次をしていた時に永井荷風と出会い、大正3年に籍を入れますが、翌年離婚。永井荷風の浮気癖に、静枝が三桁半を突きつけたと言われています。二人の間には入籍前に子が一人産まれていましたが、入籍前であることや荷風が係累を忌避する考えを持っていたことから、静枝の兄弟の下に養子に出されています。三代目静樹は、この子孫であり、初代からは孫にあたります。

藤間静枝(のちの初代藤蔭静樹)が大正6年におこなった舞台公演「藤蔭会」が、新舞踊運動の起点と言われています。平塚らいてうの女性解放運動や、坪内逍遥の新楽激論の影響を強く受けていました。藤蔭会で上映された長谷川時雨による新作の「出雲の於国」は、題材に於国を扱うのはもちろんのこと、舞台美術は美術家である東京美術学校(後の東京芸術大学)校長であり洋画壇の泰斗である和田英作が手掛け、ヨーロッパの要素がふんだんに取り入れられました。

また、大正9年の藤蔭会では、福地信世が"思凡"を書きました。舞台は尼寺であり中国演劇を題材としていますが、イプセンの"ノラの家"と通じるものを思わせ、自由と解放を求める踊りとなっています。他にも静枝自身の舞踊への情熱もさることながら、田中良、香取仙之助、遠山静雄、町田博三(佳声)などの文化人から、新しい時代の息吹を吹き込むべく演出・作詞・作曲・美術・照明などで藤蔭会に協力がありました。その中で生み出されたのが"落葉の踊り"や"秋の調"などの歌詞のない器楽曲の振付、洋楽伴奏の踊り、群舞作品などであり、いずれも近代ヨーロッパの影響をうけ、作り出されています。
一方、藤間流の家元二世藤間勘右衛門も、静枝が踊りの道に入った修行時代も新しい方向を目指してからも、常に深い温情で見守ってくれたこともあり、静枝は恩師として深く畏敬していました。しかし、静枝の新舞踊運動が進めば進むほど、伝統芸能と相入れられない部分が増え、昭和6年に藤間流を離れて藤蔭流を創流することになりました。
昭和になって新舞踊運動はより一層盛り上がり、昭和4年には静枝はパリ公演を行いました。しかし、この最も活動が盛んな時期に影を落としたのが、第二次世界大戦でした。戦時下では、愛国行進曲や君が代変奏曲などを踊らねばなりませんでしたが、静枝の舞踊への情熱は衰えませんでした。
昭和32年に弟子の美代枝に静枝を譲り隠居して静樹と名乗りましたが、二代目とは後に不和となり、昭和33年に藤蔭流宗家を樹てました。昭和39年、病床についた静樹に文化功労者の栄誉が贈られました。そして昭和41年の静樹の没後、全国の門弟が一丸となり藤蔭流藤蔭会を発足させ、今日に至ります。


